
建築の仕事に憧れ、最初は建築系の学科を考えていましたが、“ものづくり”という点では土木系を選ぶべきか悩んでいました。そんな時、九工大では両方を学んだうえでコースが選択できることを知り、迷わず進学。私は最終的に土木を専攻しましたが、建築分野の知識も得られたことで多角的な視野が持てるようになったと思います。3年次では実験を通して土木分野の実践的な知識と経験を習得。所属する研究室では、セメントを使わない新素材「ジオポリマー」について研究しています。私は「沖縄県産ジオポリマーの実現」を目的に、地元企業の協力も得ながら進めています。来年度は大学院に進み、研究を続けるつもりです。
日比野誠・合田寛基研究室 松山西中等教育学校(愛媛県)出身
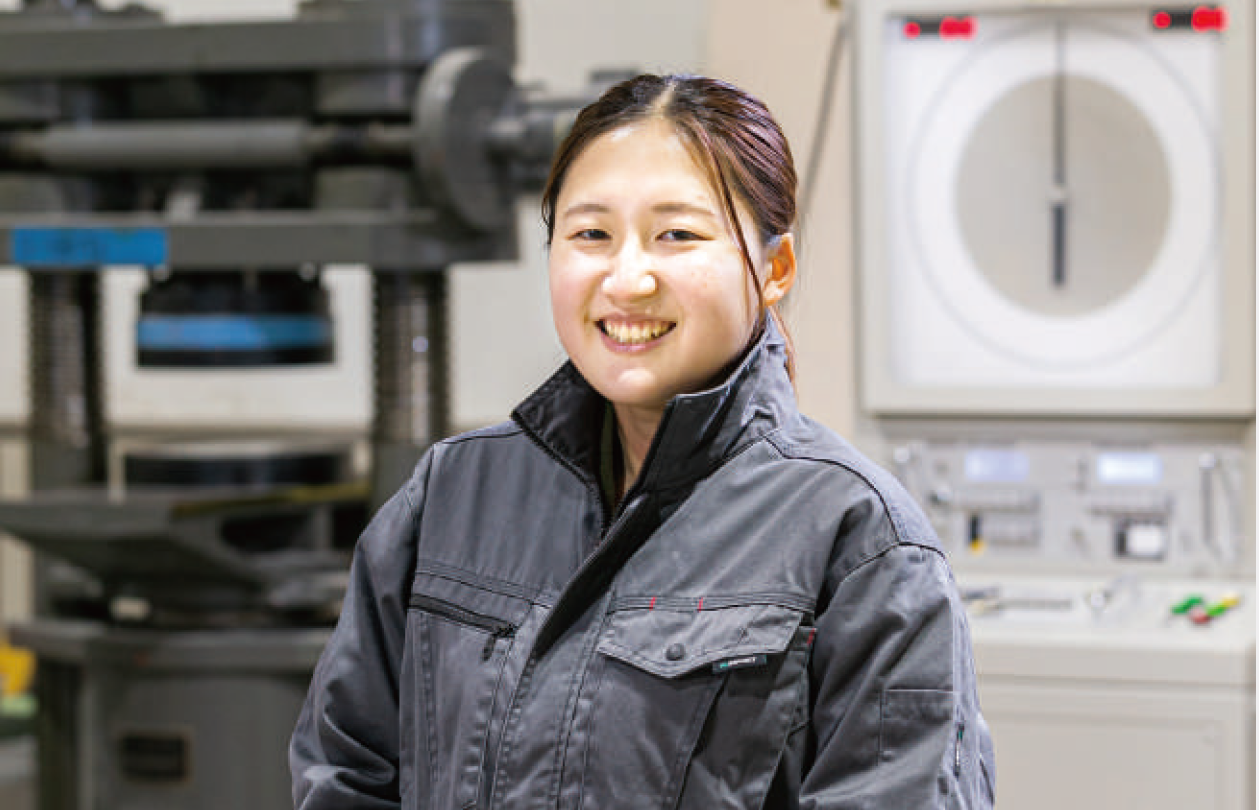
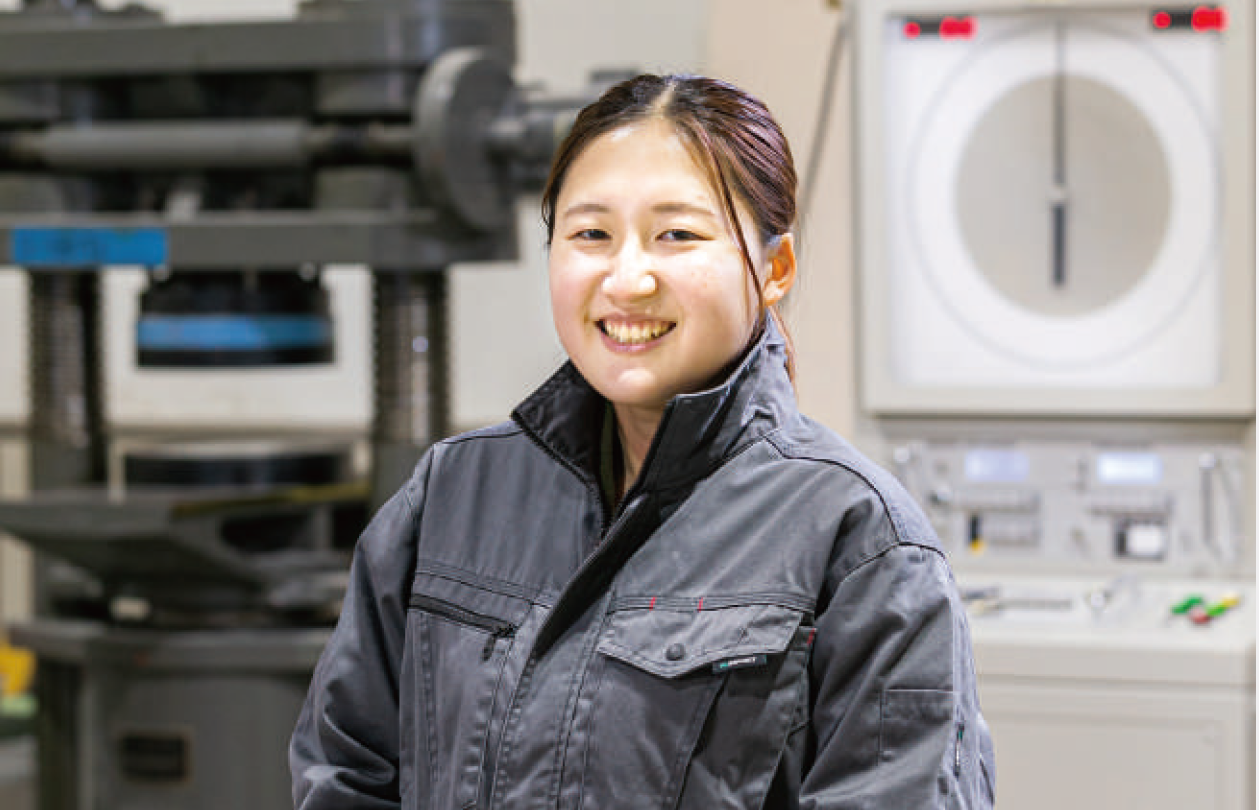
理系の大学のなかで、さまざまな分野で活躍している先輩が多い九工大を志望しました。機械工学を選んだのは、理系の中でも物理が得意だったため。1年次、CADというソフトを使って行なった図面設計、2年次の材料力学や流体力学、3年次の設計製図など、新しい学びを通して、できることや知識が増えていくことが楽しいです。また、難しいからこそ習得したときに大きな達成感が味わえます。現在の研究テーマは、金属疲労について。材料が疲労することは、ものが壊れる原因であり、安全性にも大きく関わってきます。将来はこの研究を活かし、設計の仕事において安全なものづくりをしたいと思っています。
黒島義人研究室 佐世保北高等学校(長崎県)出身


1年次からロケットや人工衛星を作れること、衛星の打ち上げ実績があることに魅かれて九工大へ。印象的な授業は3年次「宇宙工学PBL」。それまでに習得した知識を使って宇宙工学を実践的に学ぶもので、学生自らプロジェクトを計画、実行しなければなりません。私たちのグループはモデルロケットの打ち上げをテーマに活動。“ものづくり”そのものより、そのために何が必要なのかを分析するのが大変でしたが、そのプロセスは現在研究を進めるうえで役立つています。手がけているのはハイブリッドロケットエンジンを設計するための基礎研究。課題は山積みですが、そのロケットで火星へ行くことを目標にがんばっています。
北川幸樹研究室 口加高等学校(長崎県)出身


高校時代、“ものづくり”というだけで、具体的な目標がないことが悩みでした。そんな時、九工大のオープンキャンパスで電気電子の先生の「うちなら何にもなれるよ」の言葉に魅かれて進学を決意。ここなら、何でも挑戦でき、将来の選択肢が広がると思ったのです。授業は実験も多く、学んだ原理の現象を実際に目にすることで知識と結びつき、苦手な分野もおもしろいと感じるようになりました。研究室では半導体技術を利用した新しい医療技術「滅菌法」を研究しています。以前は想像さえしなかったことですが、電気電子の学びが医療に役立つのです。将来は、医学と工学、両方の視点から医療機器や技術開発に携わりたいです。
和泉亮研究室 広島新庄高等学校(広島県)出身
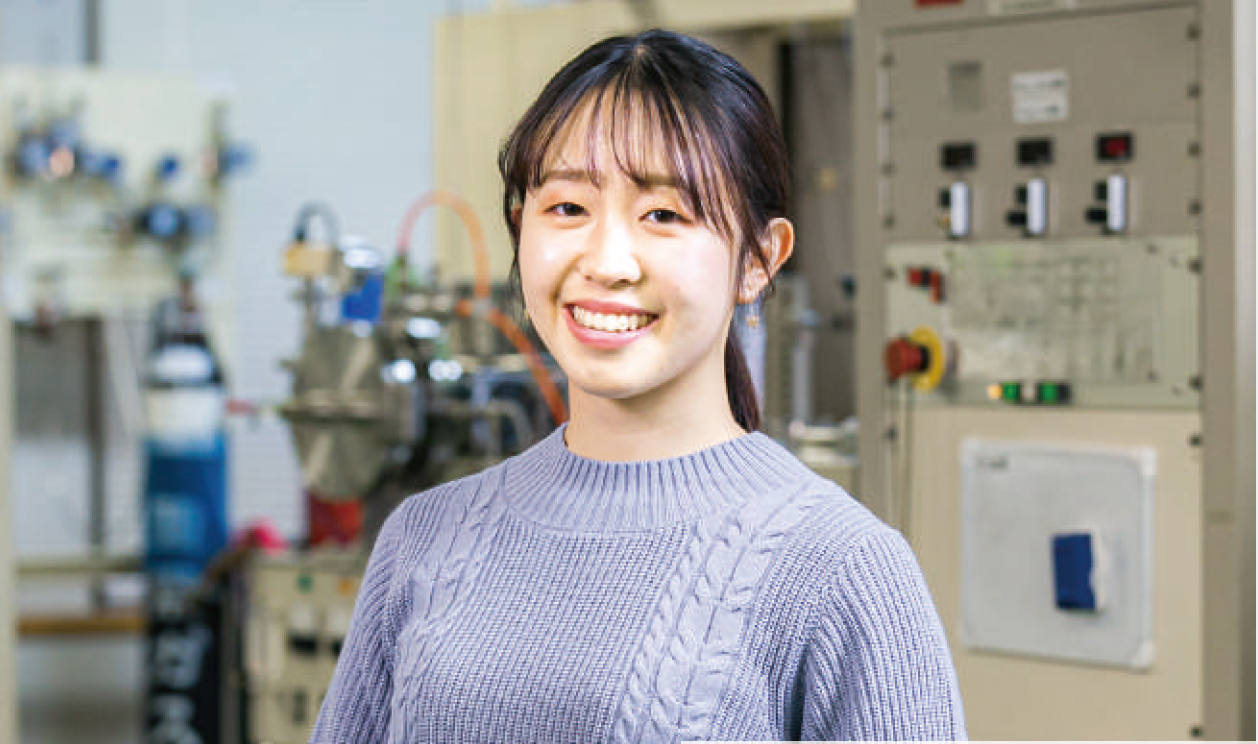
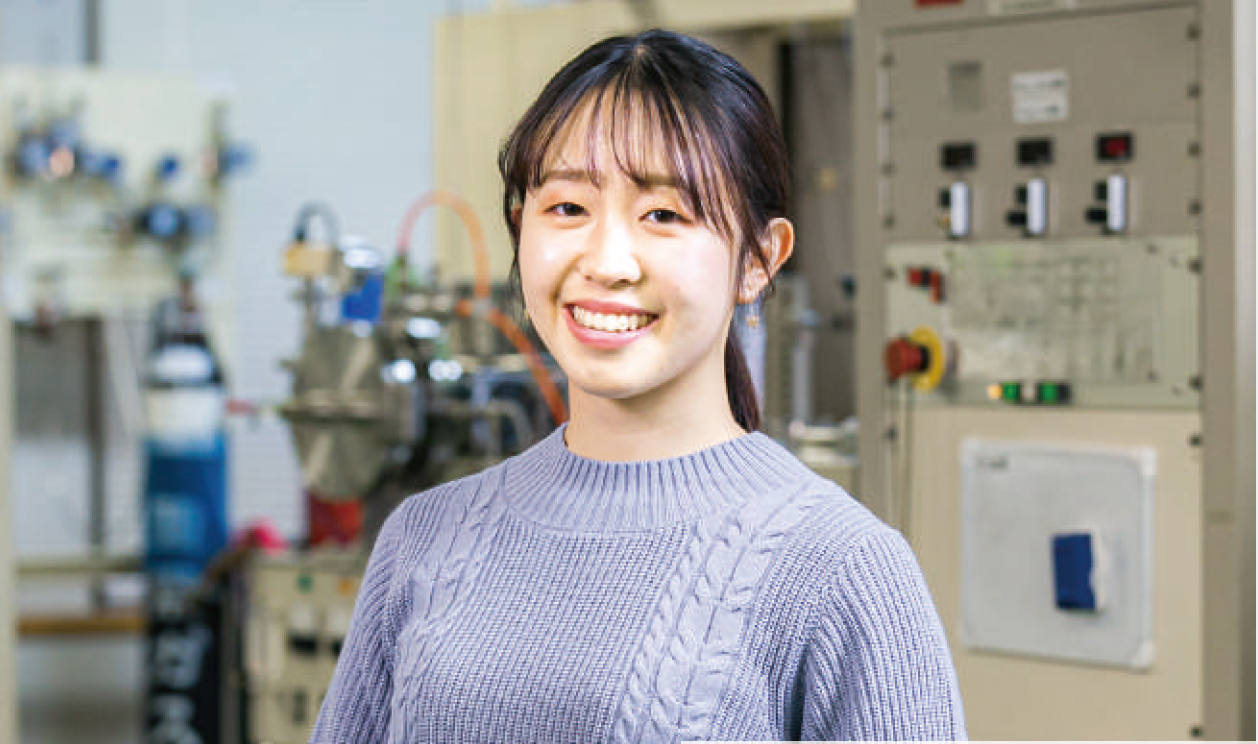
有機化学や高分子化学が学べる大学を探す中で、就職や国際交流に力を入れている九工大に魅力を感じました。2年次から始まった学生実験は予習にレポート課題と苦労しましたが、この経験が一人で研究を行う“今”に活かされています。現在手がけているのは、形状記憶性や自己修復性をもつポリマーの開発です。形状記憶や再生機能の他、構造の一部を変えることで違う性質を持たせることができるのがおもしろい点。これらを活かし、例えば、修復できるスマートフォンのガラスを作れば、新しく買うのではなく、再利用が可能になります。環境に優しく、暮らしを豊かにする材料を生み出すことで世の中に貢献したいです。
吉田嘉晃研究室 久留米高等学校(福岡県)出身
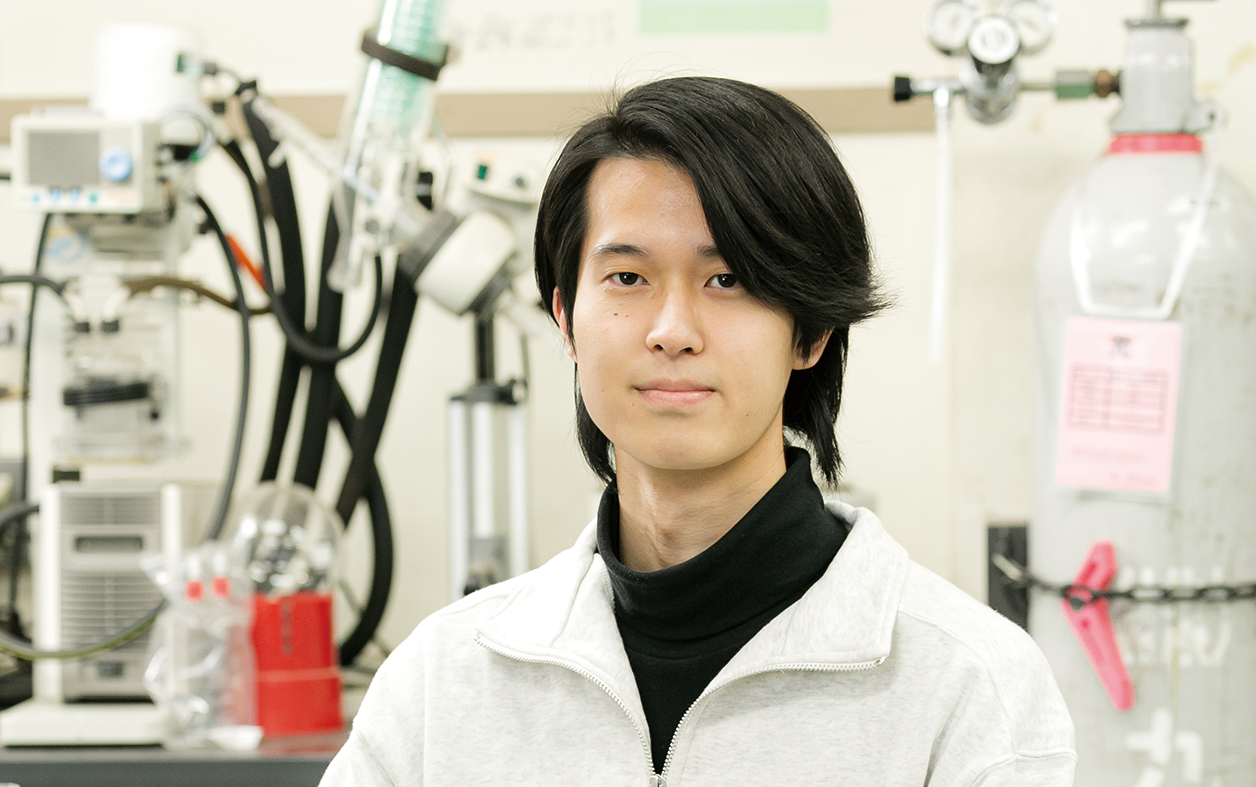
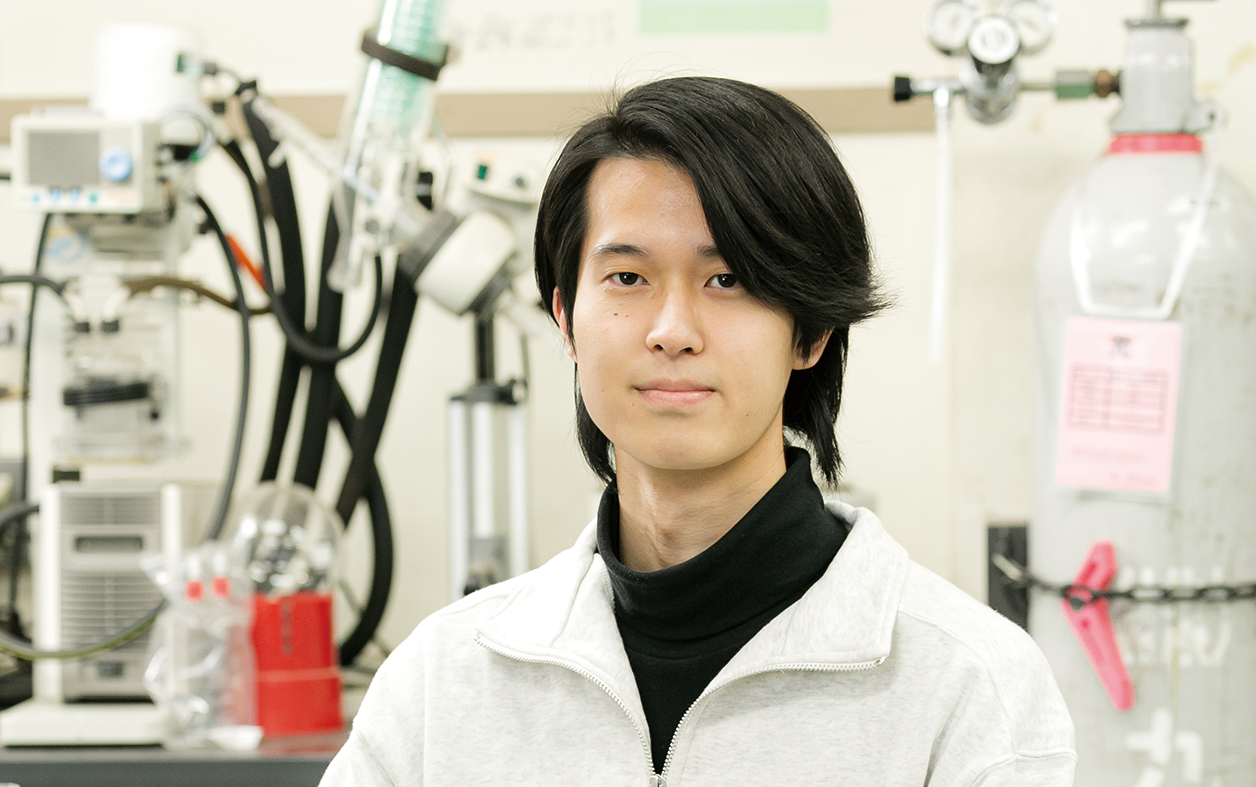
学部での授業は座学から実習まで幅広く、特に興味を持ったのは3年次の実習の授業。マテリアルが持つ微細な構造(ミクロ組織)を観察したり、自分で測定したデータから状態図を作成したりと、今まで座学で学んだ知識を実際に体験し、理解を深めることができました。現在の研究では、鉄系材料を対象として、添加する元素の種類や量によって様々に変化するミクロ組織を明らかにしようとしています。鉄系材料は世の中で広く使われており、ミクロ組織制御により優れた特性を引き出すことは、この材料の新たな可能性を拓くことにつながっていきます。将来はものづくりを支える工具の世界に進み、材料開発に携わりたいと考えています。
徳永辰也研究室 島原高等学校(長崎県)出身
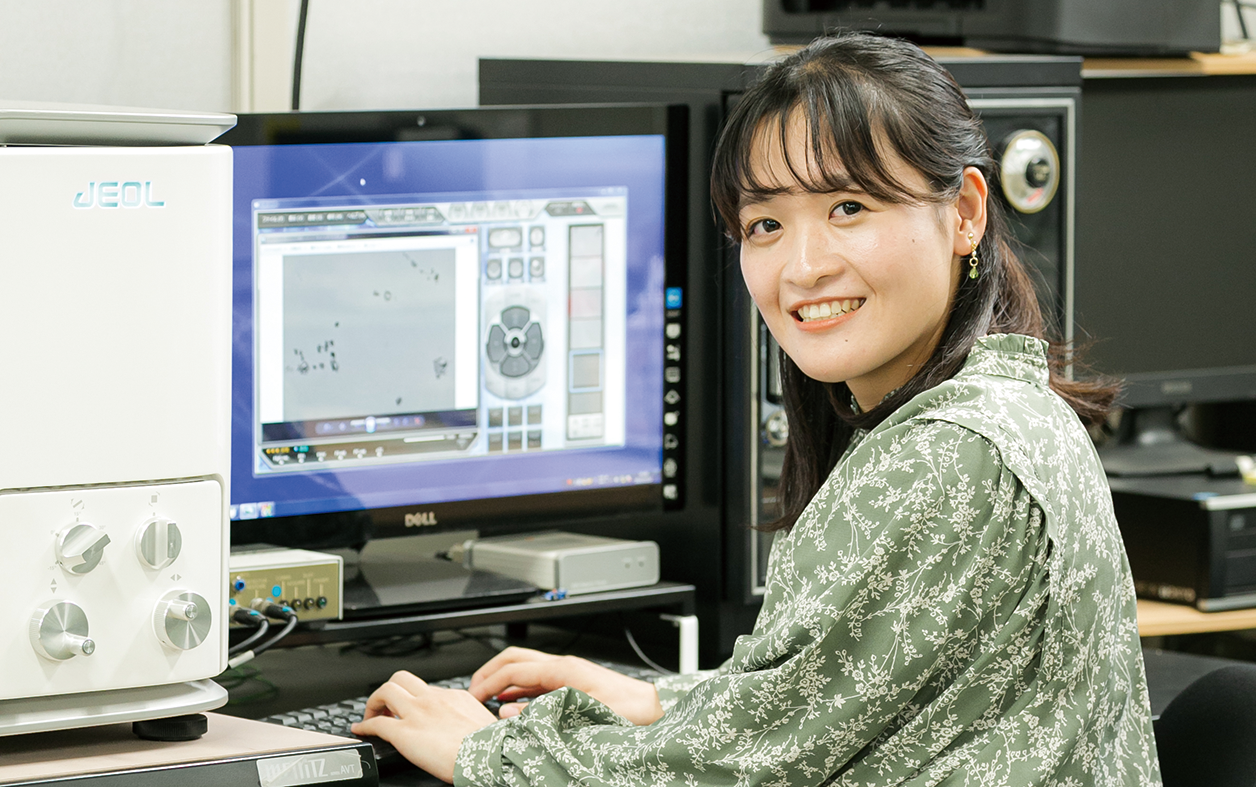
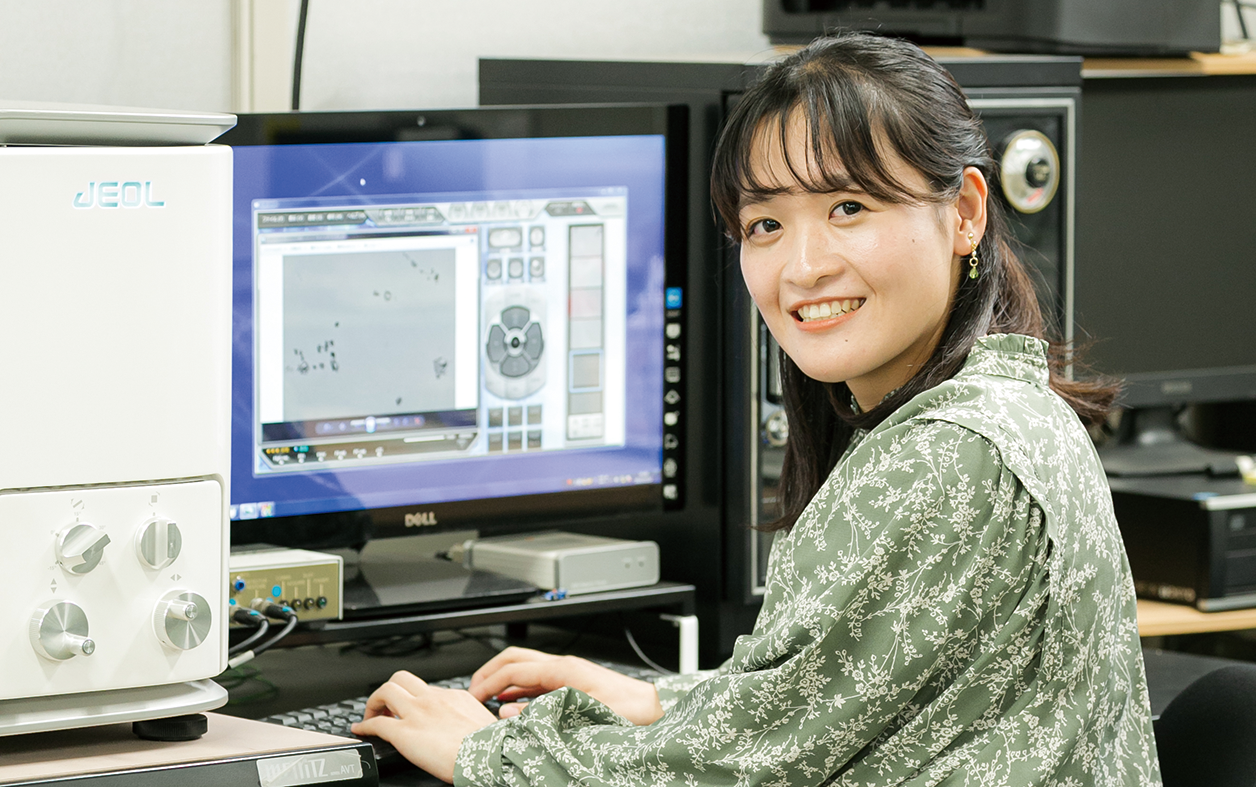
高校生の時、九工大に人工知能コースが新設されることを知り、これからの社会を担う分野への期待感と好きな数学を活かせるデータサイエンティストへの憧れから進学を決意。1年次のプログラミングの授業は魔法使いになった気分で夢中になりました。4年次に企業との共同研究に参加したことも良い経験です。自身の研究が社会に還元できることが自信につながり、産学連携に取り組む九工大だからできたことだと思います。現在は、少ない作業コストで導入可能なAIや画像の異常検知技術などを研究。製造業におけるAIとの協働により、人間はより創造的なタスクに集中でき、これが新たなイノベーションの創出につながると考えています。
徳永旭将研究室 自由ヶ丘高等高等学校(福岡県)出身


モノをインターネットでつなぐIoTは、私たちの生活や産業に革命をもたらすものだと思っています。その基盤技術となる通信についての知識とスキルを学ぶため本科を志望しました。学びの中で、これまで何気に使っていたインターネットの裏側はとても複雑で多くの研究によって成り立っていることを知り、とても感動したことを覚えています。現在は、いかに効率的に通信できるかについて研究しています。第5世代通信である「5G」、さらにその次の世代となる「Beyond 5G」に関する実験も手がけられる研究室を含め、九工大は自分のやりたいことをやり、成長できる環境が整っていることを実感しています。
塚本和也研究室 宮崎日本大学高等学校(宮崎県)出身


多彩な分野の研究室が充実している知的システム工学科に惹かれて九工大を志望。高校生の時は、漠然とものづくりに携わりたいと考えていたのですが、本科なら学びの中で興味がもてる研究に出会えるのではないかと考えたからです。プログラミングや線形代数など基礎を習得した1年次から、チームでのロボット製作も手がけた3年次まで、充実したカリキュラムを受ける中で私が興味を抱いたのは「制御」という分野です。現在、制御の検証モデルのブロック線図を、プログラムを使って効率的に生成する手法について研究しています。大きなシステムを扱う際には効率が求められるため、重要な研究だと思っています。
古賀雅伸研究室 修猷館高等学校(福岡県)出身


正直、入学当初は具体的な将来像はもちろん、なにを学びたいのかさえわかっていませんでした。そんな私の転機は、「生物物理学」の授業です。生物は暗記科目のイメージだったのですが、物理法則を用いることで生命現象が説明できることを知り、とてもおもしろいと感じたのです。これをきっかけに、もともと好きだった生物について学びを深めたいと思いました。現在は、細胞のシグナル伝達機能について研究しています。体内の細胞はシグナル伝達を用いて互いにやりとりをしているのですが、その詳細の多くは解明されていません。私は細胞が小さいためだと考え、細胞を巨大化させて現象観察の実現を目指しています。
森本雄祐研究室 嘉穂高等学校(福岡県)出身
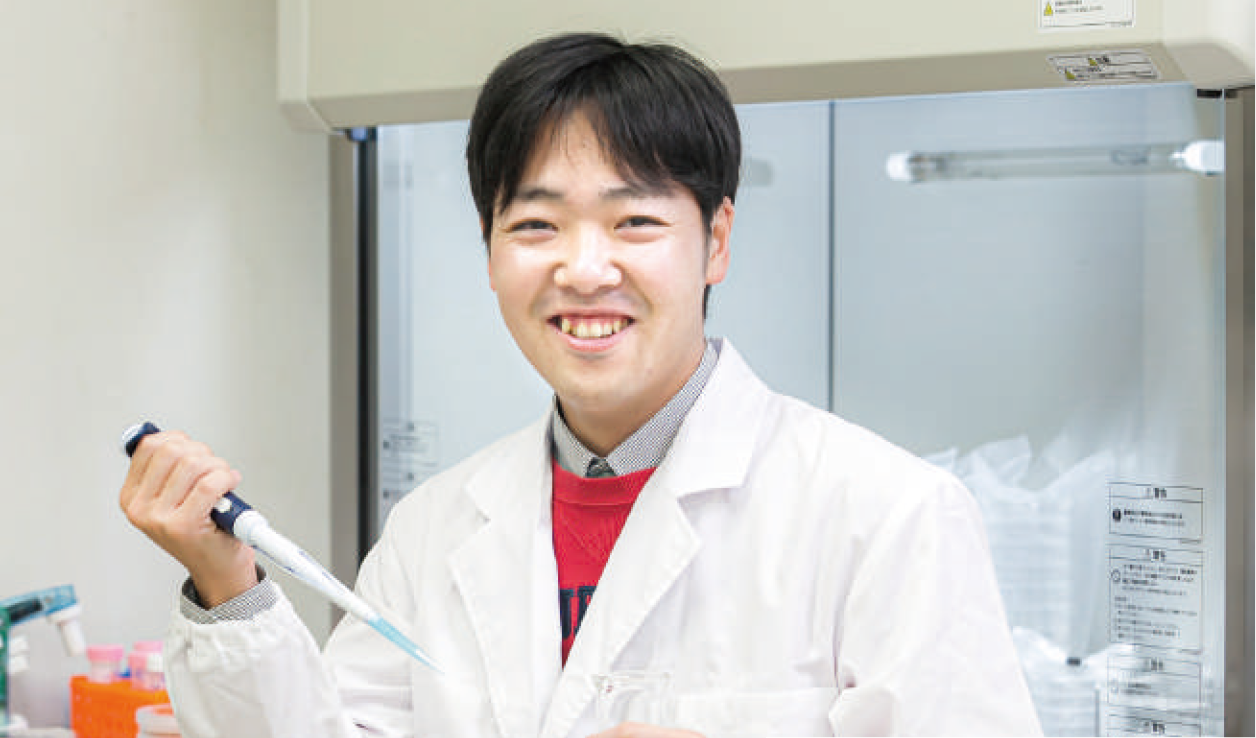
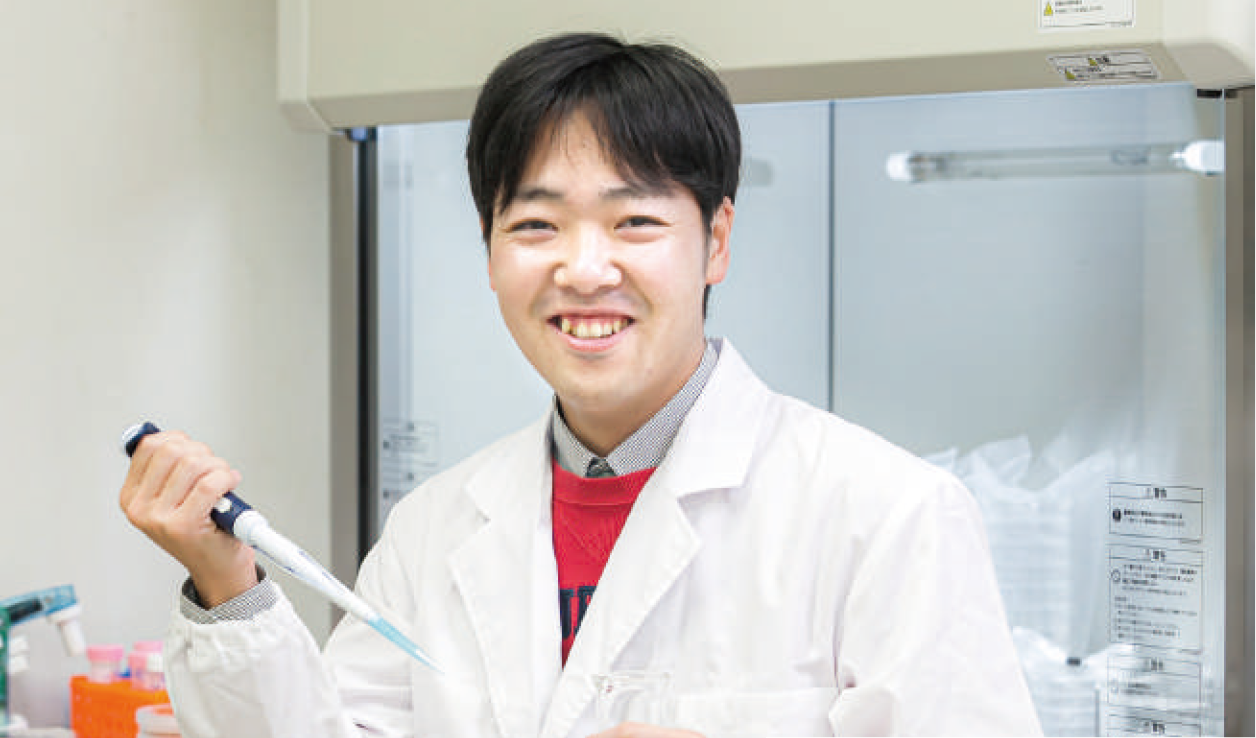
生命化学の視点のみならず、情報工学からも医療にアプローチできるこの学科で学びたいと志望。私が目指す健康寿命延伸の分野をテーマにした研究室が充実している点にも惹かれました。中でも医用画像診断AIの脆弱性評価を行う竹本研究室に興味を持ち、現在その研究室に所属しています。私の研究テーマは、「ChatGPTの医療質問応答の精度評価」。将来的には診断の一部をAIに一任できるようになるかもしれませんが、現状その信頼精度は不明瞭です。そこで、ChatGPTがどの程度正確な応答を返すことができるのか体系的な評価を行っています。学部卒業後は大学院に進み、研究を深めるつもりです。
岩竹本和広研究室 西南学院高等学校(福岡県)出身

